今年は梅雨が短かったわけですが、選挙が終わると同時に雨模様にもどり、恒例の線状降水帯に悩まされております。実家の周りも脛まで水があがり、近所では床下浸水があったそうです。温暖化や異常気象はさておき、穏やかでないことはたしかです。
その豪雨で気温が少しさがってくれるのはありがたいのですが…
見過ごせないので歴史的事件にすこし触れますが、その選挙中に元首相が暗殺され、その数時間後に外国では関係する宗教団体名が報道され、日本では選挙が終わって明らかになり、過去に大騒ぎしたことを多くの若者は知らない。それだけ自分が歳をとったことを感じつつこの国のありかたを考えていました。
自国民が事実をしらされず、海外で先に報道された結論は「マスメディアは信じるにあたいせず、情報はグローバルコントロールされている」ということでしょうか。
書きだすと論点が敗戦処理(GHQ、東京裁判、WGIPなど)までさかのぼるので深く書きませんが、いま日本人に必要なことはマクロで物事をみる練習だと思います。今回の事件で言えば敗戦から立ち直る仮定で反共産という社会、だけど教育には共産的一面。
残念ながら国民が貧乏になりすぎてミクロに意識が向きがち。今回の選挙の争点は与党信任の是非だと思いますが国民が貧乏ゆえに「物価高騰」という超ミクロなことに目がむき、マスコミもそれを担いであざむく体。
それでも一部の善良な人々が時折まともな情報を発言し、それを受けた私も「たしかに何かがおかしい」と感じます。なにより不思議な感覚は敗戦までは良くも悪くも一枚岩の国家が80年という歳月をかけて木っ端微塵に瓦解する最終段階に生きている感覚。
そういった不思議な感覚を察知している人が増えているのでは?と思います。
これは動物的感なので、なにも感じない人もいると思います。
起こっている現実を論理的に理解するというよりは、まったく整合性がつかない状態にまで社会が歪みすぎて知りたくもないのに知らざるをえないところまで行き着いた感覚。
動物番組でアフリカのライオンやチーターがガゼルやヌーに忍び足で近づき、射程距離に入ると一気に、一瞬で獲物を捉える。ライオンやチーターの最初の蹴りを察知したと同時に気付いて逃げる動物もいれば、数秒遅れで命を落とす動物。
最初の蹴る足音を感じられる人が増えた年に感じます。
命を落としたくなかったら全力で走り、何度も右へ左へと90度方向を変えて振り切る。
その状況を俯瞰して妄想できる人は、獲物を捉える行動に至る前に群れからはぐれた動物や群れから引き離す戦術を見抜ける人もいるわけですが、それが成せる理由は考えぬく量に比例しますから詰まるところ教育が大事ということでしょうか。
一連の事件に対し田中真紀子さんの言葉とモノマネを思い出しました。
「伏魔殿 + たいへん根深いものがある」みたいな感じ。
与党がダンマリなのはわかりますが野党もダンマリですから侵食ではなくそれが通常営業になっていると予想し、これを根本から解決するには「戦後レジームからの脱却」として解党に至る気がします。戦後からずーっとですから。

ネットには関係者一覧なる情報も出回っているのですが、問題はそんなミクロなことではないと思います。私が思うに、戦後密約でも交わされ、1970年ごろ社会で表面化し、1990年代の大騒ぎ以降(つまり失われた30年)から今日にいたるまでは公然の秘密になり、党の公認を受けたら自動的に宗教の公認も受けるパターンではないかと感じました。もはや夫婦のようなあうんの呼吸。だから与党はダンマリを決めこめる。
結果として志をもって政治家になった人が信者でなくとも表向き良さげな宗教イベントに登壇したり雑誌の表紙を飾ったりする。すでに政治から離れた人も叩けばほこりがでなるのでは?と思います。当選後自ら首を突っ込んでズブズブになる人もいれば、気付いて距離をおく人もいれば、いまだに気づいてない人もいるかもしれません。
本来無関係の政治家に宗教関係者が忍び寄ることもあるでしょうから、事は政治家だけの問題ではなく国民側も気を付ける必要があります。よかれと思える愚行に気づけない人々。私からみれば国全体が伏魔殿の印象。
なんで日本はこんなことになっているのか?なんで外国でも似たことが起きているのか?
一般的にはマインドコントロールと言われますが、日本おいては国家国民全体がソウルコントロールまで深化しすぎて制御不能に感じます。ちなみに私の思うソウルは魂ではなく、もっと平易に理解できる「伝統文化」。TraditionalとConservativeをミックスしたイメージ。そんなことを考える日々でした。
もちろん何かをひらめいたときは新たな別の嘘が隠されていることもあるので慎重かつ大胆な胆力が求められ、とかくナショナリズムへ傾倒するときはよくないことが起こりうるので皆が勉強して賢く行動する必要もある。
さて、私にとってそれら得体の知れない時空をうめる方法はそれ以前の日本を知り、比較することで「だから消えたのか」とか「だから残ったのか」と自分で頭の整理をすることがとても楽しく感じます。
(いつもの現実逃避)
いまのように赤ちゃんとして産まれた瞬間から消費者やコストとして見ざるをえない極端な状況への苛立ちを和らげてくれる薬のようなものです。本日は「」なるビジュアルブック。
以前にも同種の本をメモしましたが、今回は以前のそれより少し解説が多く、日本語表現も丁寧で綺麗で豊かです。

染み入る部分を少しつまみ食いしますと…
日本を訪れる外国人は、先ず最初に、日本人が花を愛することの印象を受ける。どこにでも、庭内に、あるいわ小さな水槽の中に、植木鉢やぶら下がる花入れや立っている花入れがあり、そして外国人は、日本人が花を生ける方法の簡潔さと美しさとが、いたる所に顕れていることに気がつき出す。
※いまの日本人が花を愛する印象はないような気が…

それは日本が子供達の天国だということである。(中略) 赤坊時代にはしょっ中、お母さんなり他の人なりの背に乗っている。
※ベビーカーに乗っている印象しかないよね。肌が触れ合うことが大切では?
この国の人々の芸術的性情、いろいろな方法(極めて些細なことにでも)で示されている。子供が誤って障子に穴をあけたとすると、四角い紙片をはりつけずに桜の花の形切った紙をはる。
※障子が疎遠な住宅環境でもイメージはわきます
いちいちうなずける言葉ばかりですが、じゃあモースコレクションがいまの日本で絶滅したか?というと、その多くは今でも伝統文化として残っているのですが、それはあくまでも伝統工芸品としてであり、生活からほど遠い昔話のような実用性のない状態ですから、いわば化石のようなものです。それらも維持が限界に達し人知れず消えようとしているのでは?と思います。
でもこうして目にすると「あぁ、なにか、どこか懐かしい」と感じます。
これこそが「日本人のソウル=伝統文化」だけど現実は否定した生活の連続。もう少し大切にしてもよいのでは?と思います。日本人が大事にしなかったら誰が大事にするのさ、みたいな。

本の英語タイトルは「Soul of Meiji」で日本語タイトルが「明治のこころ」。
つまり日本人の精神性であったり、民族特有の感性であったり、自然との共存であったり。良いタイトルですよね。マインドの素となるソウル。ソウル(魂)を心と訳してるのがミソ。
心をカタチにしたものが日本の伝統文化そのものと解釈できる内容です。
モノが溢れる世界に生きていると質素で簡素に見えますが、当時の庶民生活は今でいうミニマルであったことを思うと「これでも十分華美な装飾かもなー」なんて思いながら読み返しました。日本人の美意識が自然とともに育まれてきたこともよく理解できます。
私の親や祖父母世代は極端にモノがない貧しさを経験していますが心は豊かだったと聞きますが、わたしはモノはあっても極端にソウルがない貧しさを今の日本に感じています。「」おすすめの一冊です。


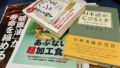

コメント